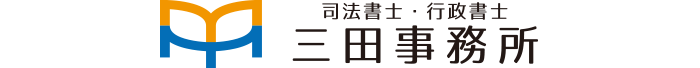被相続人Aには妻Bと子C・D・Eがいるが、生前「自宅とその敷地である所在○○の不動産はCに相続させる」という内容の遺言を作成しました。この遺言は、特定の財産を特定の者に与えているのであるから遺贈として扱うべきでしょうか。それとも、現物分割という遺産分割方法の指定として扱うべきでしょうか。遺贈として扱われると、A所有の不動産の名義をCに移転する登記申請をするには、受遺者である相続人Cと遺贈義務者である他の共同相続人B・D・Eとの共同申請をする必要があります。この場合、他の共同相続人の1人でもこの遺言に不満があるとして登記申請に協力しないとなると、Cは裁判所に訴訟を起こして判決を得なければなりません。これに対して、遺産分割方法の指定として扱われると、相続登記の問題になるから、他の共同相続人とは無関係に、Cは単独で相続登記の申請をすることができます。ただし、上述の遺贈として扱われる場合における登記申請の方法については、不動産登記法の改正により、相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、相続登記の申請と同様に、受遺者である相続人が単独で申請することができるようになりました。この取扱いは、令和5年4月1日以後にされる登記申請について適用されます。なお、相続人以外の者に対する遺贈における登記申請は、従来通り受遺者と遺贈義務者との共同申請となります。
この法改正によって、「相続させる」旨の遺言が、遺贈として扱われるのか、それとも、遺産分割方法の指定として扱われるのかで、所有権移転登記の申請における違いは無くなったことになります。しかし、受遺者である相続人が、その遺言による財産の取得を望まない場合において、その取得を放棄するときに違いが生じます。遺贈として扱われると、特定遺贈となるので、遺贈のみを放棄して、他の相続を承認するということができます。これに対して、遺産分割方法の指定として扱われると、相続放棄をすることになりますが、そうなると、遺言による財産の取得だけでなく、他の相続も放棄することになってしまいます。
この点について、最高裁判所の判例は、「相続させる」旨の遺言は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、特定の相続人に特定の財産を取得させることを指示する遺産分割方法の指定を定めたものであり、原則として、何らの行為も要せず、被相続人死亡時に、直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるとしました。そのため、上述のような場合では、受遺者である相続人が遺言による財産の取得を避けるためには、相続放棄をして他の相続とともに一切の相続を放棄するか、他の共同相続人の合意を得て、当該財産も含めて遺産分割協議をして、他の共同相続人の誰かに当該財産を取得してもらうことになります。しかし、後者の方法は、他の共同相続人の1人でも合意が得られないと、遺言の内容どおりに当該財産を取得しなければならなくなります。
このように、遺言作成しても、その内容によっては、遺言者の意思が十分に反映されなかったり、かえって残された相続人を困らせてしまったりすることがあります。遺言者の意思を十分に反映させ、相続人も納得できる遺言を作成するには、専門的な知識と見識が不可欠です。遺言の作成を検討される際には、弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
(司法書士・行政書士 三田佳央)