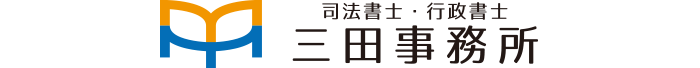相続人は、相続が開始すると、被相続人の一身専属権を除き、被相続人に属する一切の権利義務を承継します。そのため、相続人は、被相続人に帰属した債務をも、その法定相続分に応じて承継することになります。債務のうち、動産や不動産の引渡義務などの不可分債務については、遺産分割によってその帰属する者を確定させることになります。なお、賃料債務については、目的物全体に対して使用収益をする地位にあるので、これに対応して共同相続人の不可分債務だとするのが判例です。
これに対し、可分債務については、相続が開始した時にその法定相続分に応じて分割して帰属することになるため、遺産分割の対象とはなりません。しかし、被相続人は遺言によって法定相続分と異なる相続分を指定することができ、このことは可分債務についても当てはまります。遺産分割についても同様に考えられます。このような遺言や協議は、相続人間においては有効です。
ただし、この遺言や協議は、相続債務の債権者の関与なくしてなされたものであるから、その相続債務の債権者に対しては効力が及びません。そのため、各相続人は相続債務の債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を請求されたときには、これに応じなければなりません。そして遺言や協議で定められた額以上の債務を弁済した相続人は、その分を負担すべきであった相続人に対して、不当利得返還請求をすることになります。
もっとも、相続債務の債権者から、相続債務についての遺言や協議を承認し、各相続人に対して、遺言や協議の相続分に応じた相続債務の履行を請求することもできます。これは、相続債務についての遺言や遺産分割協議の効力を有効として、相続債務に対する権利行使については、相続債務の債権者に選択を委ねることによって、相続人側の事情と相続債務の債権者の利害を調整するためです。
連帯債務者の1人である被相続人の連帯債務は、相続の開始によって、各相続人は、その債務の分割されたものを承継し、各自その範囲において、他の連帯債務者とともに連帯債務者となるとするのが最高裁判所の判例です。これは、連帯債務は、数人の債務者が同一の給付につき各自独立して全部の給付をなすべき債務を負担しているが、可分であることは通常の金銭債務と同様だからです。例えば、債権者Aに対し、BとCが900万円の連帯債務を負担部分2分の1ずつ負担している場合において、Cが死亡しその子C1・C2・C3が相続したとすると、C1・C2・C3は各自300万円の範囲でBと連帯債務者となります。
(司法書士・行政書士 三田佳央)